食べる時にクチャクチャ音がする。咀嚼音の原因と歯科医院でできる対処法を解説
2025/04/20
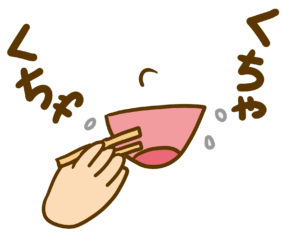
こんにちは、都筑区(都筑ふれあいの丘駅)の歯医者、マサキ歯科クリニックです。
咀嚼音とは、食べ物をかむときに発生する音のことです。
食事中に自分や周囲の咀嚼音が気になったことは、誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
中でも「クチャクチャ」という咀嚼音は、周囲に不快感を与えやすく、音が大きいことで「マナーが悪い」「清潔感がない」などといった印象につながることもあります。
そこで本日は、咀嚼音の原因や改善策について解説します。
咀嚼音の原因
歯並び・かみ合わせの悪さ

咀嚼音が大きい場合の主な原因として、歯並びやかみ合わせの悪さが挙げられます。
かみ合わせが悪いと、無意識に口が開いた状態になることが多く、これが音の発生の原因です。
例えば前歯が前方に突出していると、きちんと唇を閉じて咀嚼することが難しくなるため、音が発生しやすくなります。
また、下顎が受け口状態にある方も同様です。さらに、かみ合わせのバランスが不均衡な場合にも、特定の歯で集中してかむことになり、咀嚼音が生じやすくなります。
口呼吸

鼻呼吸を行っている場合は口を閉じたままでも息ができるため、口を閉じて咀嚼することができます。
しかし、口呼吸をする方は口を開けたままでないと息ができないため、口を開けて咀嚼してしまうことで「クチャクチャ」という咀嚼音が周囲に響きやすくなります。
口呼吸の主な原因は口周りの筋力の弱さや、鼻づまりやアレルギー性鼻炎などです。
場合によってはライフスタイルや環境要因が影響していることもあります。
口周りの筋力低下
口の筋力低下が原因となって咀嚼音が生じることもあります。
口の周りには口輪筋という筋肉がありますが、この筋力が低下すると、口を閉じて咀嚼するのが難しくなり、音が発生しやすくなります。
また、舌の筋力が低下することで、食べ物を舌で口内に運ぶ際に「クチャクチャ」という音が発生することもあります。
食べ方の癖

かみ合わせや筋力の問題がなくても、食べ方の癖が原因で咀嚼音が鳴る場合もあります。
これは、幼少期の生活環境や習慣が影響していることが多く、例えば口を開けたまま咀嚼をしていた子どもの頃の癖が、成長過程で矯正されずに残ってしまっている場合があります。
また、家族や近しい人の中に「クチャラー」がいる場合、その食べ方を正しい、もしくは問題がないと認識し、無意識のうちに模倣してしまうケースも見受けられます。
このような習慣は、大人になってからも持続することが多く、他人から指摘されるまで認識しにくい傾向があります。
唾液の少なさ
唾液は、食べ物の飲み込みをスムーズにする役割を担っています。
唾液の分泌が少ないと、食べ物が口の中でやわらかくならないために飲み込みにくくなります。
そのため、唾液の分泌量が少ない方は、口の中で食べ物をやわらかくしようと咀嚼する回数が多くなり、その分咀嚼音が目立ちやすくなることがあります。
顎関節症による異音

顎関節症とは、顎関節が何らかの原因で痛んだり、口の開閉がしにくくなったりする症状を指します。
あごを動かした際に「シャリシャリ」や「ゴリゴリ」といった音が発生することもありますが、これは関節円板が前方にずれる際の摩擦音です。
このような顎関節症の音は、本人にしか聞こえない小さな音から、周囲の人々にまで聞こえる大きな音までさまざまであり、音の大きさや種類によっては咀嚼音だと誤解されることがあります。
咀嚼音の改善方法
矯正治療を受ける

歯並びを整えるために矯正治療を受けることは、咀嚼音の改善にもつながります。
歯列矯正により、歯並びが整うと、歯全体を使ってバランスよく食べ物をかめるようになります。
これにより、口を開けずに食事することができるようになり、咀嚼音の軽減も期待できます。
口周りの筋肉を鍛える
口周りの筋肉を鍛えることも、咀嚼音の軽減に役立ちます。
例えば、風船を膨らませる運動は口輪筋を鍛えるだけでなく、呼吸の調整にも役立ちます。また、舌のトレーニングも咀嚼音の軽減につながります。
唾液の分泌を促す

唾液の分泌を促すことも、咀嚼音を改善する一つの方法です。
唾液が十分に分泌されることで、食べ物を口の中でしっかりと処理し、滑らかにかむことができるようになるため、音が出にくくなります。
唾液の分泌を促進するには、よくかむこと、水分を多く取ること、そして唾液腺マッサージを行うことといった方法があります。
また、カフェインには利尿作用があるため、カフェインが入った飲み物よりも水やハーブティーを選ぶようにしましょう。
そのほか、ストレスを減らし、リラックスすることで唾液の分泌が促進される場合もあるので、自分に合った方法で生活習慣を見直してみてください。
ゆっくりかむ
咀嚼音を減らすためには、ゆっくりとかむことが大切です。
ゆっくり食べることで、食べ物が口の中でしっかりと処理され、音が出にくくなります。
さらに、ゆっくりかむことで咀嚼回数が増えれば、唾液の分泌が促進されます。
唾液には食べ物を柔らかくし、消化を助ける役割があるため、十分に唾液が出ることで食べ物がスムーズに咀嚼されやすくなり、咀嚼音が鳴りにくくなります。
正しい咀嚼方法

咀嚼音を抑えるためには正しい咀嚼方法を心がけることが重要です。
食事をする際は、前歯で食べ物をかみ、奥歯で小さくすり潰すようにしましょう。
咀嚼中は口を閉じ、鼻呼吸を意識するようにしてください。
また、ひと口の量を大きくしすぎないこともポイントです。
食べ物を細かく切り分けてから口に運ぶことで、大きく口を動かして咀嚼する必要がなくなり、その分、音も発生しにくくなります。
まとめ
咀嚼音は、日常生活の中で多くの方が不快感を覚えることのある問題です。
周囲の人々とのコミュニケーションやマナー意識に影響を与える可能性があり、その原因はかみ合わせの崩れや筋力低下、習慣、唾液の分泌量、顎関節症などさまざまです。
改善法としては、矯正治療による歯並びの改善や口周りの筋力強化、唾液の促進、ゆっくりかむこと、そして正しい咀嚼の実践などがあります。
原因と解消法を理解することで咀嚼音を減らし、周囲の方々との心地いい環境を維持していきましょう。
マサキ歯科クリニック:https://masakidental.com/
〒224-0065 神奈川県横浜市都筑区高山6-4
電話:045-943-3111
交通アクセス
都筑ふれあいの丘駅より徒歩分
東急田園都市線『江田駅』『市が尾駅』よりバス10分
横浜市営地下鉄『センター南駅』よりバス5分
バス停:大丸 下車 徒歩1分

